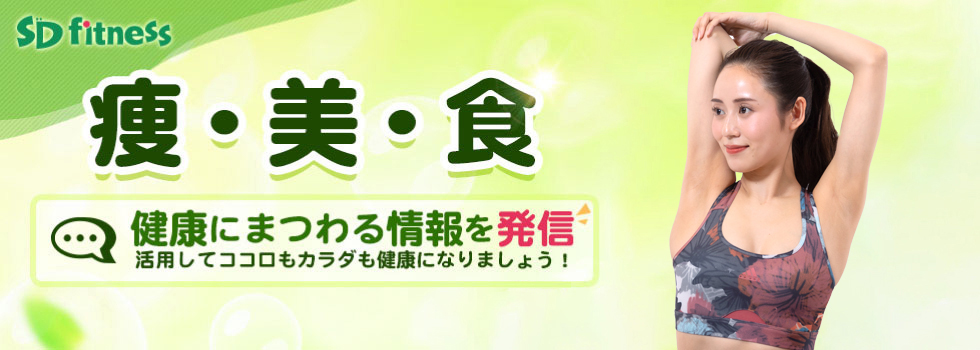炭水化物抜きダイエットは痩せる?効果を出すためのポイントを紹介
カテゴリー:痩 - Slim -
「炭水化物抜きダイエット」は、エネルギーの元になり脂肪として蓄えられてしまう炭水化物の量を減らしたり、摂取量をゼロにしたりする方法です。
ダイエットを行う際、食事制限による栄養バランスの偏りが問題になりますが、炭水化物抜きダイエットはあくまでも炭水化物のみにフォーカスするため、他の栄養素を抜く必要がありません。
この記事では、炭水化物抜きダイエットの詳しい方法や特徴、得られる効果や痩せる理由について詳しく紹介していきます。炭水化物のはたらきも含めて、ぜひダイエットの参考にしてください。

目次
炭水化物抜きダイエットとは
炭水化物抜きダイエットは、炭水化物を含む以下の食事の摂取を控えるダイエットです。
【炭水化物を含む食べもの】
-
- ご飯
- パン
- めん類
- イモ類
- 砂糖
- ハチミツ
- 果物(果糖の多いもの)
- とうもろこし
糖質は人間の活動になくてはならない栄養素の一つですが、現代的な食生活では糖質に偏りやすく、摂取しすぎることで肥満のリスクが高まります。
炭水化物抜きダイエットは糖質量を減らす、あるいは抜くことで一日のエネルギー摂取量を減らし、肥満を予防しながら体脂肪も効率的に燃焼させる方法です。
炭水化物を抜くとお腹は通常よりも満たされない状態になるため、空腹を満たすには糖質以外の食材に置き換える必要があります。そこでタンパク質や食物繊維などの栄養素を補うことができます。
炭水化物を抜くと得られる効果
炭水化物を抜くダイエット方法では、糖質からエネルギーが得られない代わりにいくつかの効果が期待できます。
【炭水化物を抜いて得られる効果】
- 摂取カロリー量が減る
- 栄養の偏りが防げる
- 食事のバランスが整う
- 血糖のコントロール
- 脂肪を作りにくくなる
炭水化物に含まれるカロリーは野菜や魚などの食材よりも高く、摂取するほどエネルギーとなり、エネルギーが消費されなければ脂肪として体に蓄えられてしまいます。
炭水化物を抜くことでご飯やパンといった炭水化物に偏る食生活が改善され、栄養のバランスも整えやすくなります。「ご飯を食べる代わりに野菜を多く摂ろう」というように、いろいろな食材を取り入れるようになり、口にする食材の品目が増えていきます。
糖質は血糖値を上昇させる栄養素としても知られていますが、炭水化物を減らす、または抜くと食後の血糖値の急上昇が抑えられ、糖尿病などの生活習慣病のリスクを低減させる役割も期待できます。
炭水化物を抜くとなぜ痩せるのか?
炭水化物の摂取量を減らすと、なぜダイエットに効果が期待できるのでしょうか。ここからは、炭水化物を抜いて痩せる2つの仕組みをチェックしていきましょう。
理由①中性脂肪が分解されるため
中性脂肪とは、炭水化物に含まれる糖質がすい臓の働きによって置き換わった物質です。体のすべての皮下脂肪と内臓脂肪を合わせたものは「体脂肪」と呼ばれますが、この体脂肪になる脂肪成分が「中性脂肪」と呼ばれています。
中性脂肪は糖質から合成される成分です。糖質は摂ってからすぐに脂肪になるわけではなく、必ず中性脂肪という成分として合成され、それらが使われなければ蓄積されて皮下脂肪や内臓脂肪となります。
中性脂肪の段階でエネルギーとして消費できれば体脂肪の増加を予防できるので、肥満症や脂肪の量が多い方は、飲食で摂取する糖質の全体量を減らすことが重要です。
理由②分泌されるインスリンの量が減るため
血糖値が上昇すると、ホルモンの一種である「インスリン」がすい臓の細胞から分泌されます。すい臓は胃の裏側にあり、食べ物を消化するための「すい液」を作って、胃で消化された物をさらに消化して十二指腸に送っています。さらに、血液中を流れる糖分の量を調節するためにインスリンも生産しています。
糖分調節のためにインスリンが分泌されると、血液中の糖の濃度(血糖値)は下がっていきます。余った糖はインスリンによって「中性脂肪」と呼ばれる物質に変換され、脂肪細胞の中に蓄えられていきます。
インスリンがたくさん分泌されて中性脂肪に置き換わるほど肥満へと繋がるので、反対に糖質の摂取量を減らしてインスリンの分泌量を抑えられれば、脂肪に置き換わる量も物理的に減らすことができます。
炭水化物抜きダイエットに取り組むメリット・デメリット
炭水化物抜きダイエットには効率的に脂肪を減らせるメリットが期待できますが、意識しておきたいデメリットもあります。取り組みやすさやリバウンドのリスクなどについてみていきましょう。
メリット
炭水化物は一日の中で必ず口にするものですが、間食(おやつ)なども含めると摂りすぎてしまう場合があります。糖質の摂りすぎは肥満や生活習慣病の原因になるため、糖質の摂取量を物理的に減らしていけば脂肪を蓄えにくい状態に改善できます。
糖質以外の栄養素が摂取しやすくなるメリットも期待できます。普段どおりに炭水化物が摂取できないので、野菜を含むローカロリーの食材を多く摂るようになり、食事の偏りが改善されやすくなります。
今まであまり食事のメニューにこだわっていなかった方も、糖質制限中は食事の内容や栄養の配分を考えるようになるので、口にする食材の品目が増えたり、栄養バランスが整ったりと、さまざまな栄養素が摂り入れやすい状態になります。「炭水化物頼り」の状態から抜け出せるので、健康や食事への意識が向上する可能性もあるでしょう。
デメリット
炭水化物を抜くと、今までスムーズに摂取できていたエネルギーが減るので、体は飢餓状態に近づいていきます。糖質を減らす量にもよりますが、一気に摂取量を落としてしまうと体は危険を感じ、脂肪を溜め込もうとするため痩せにくくなってしまいます。
糖質を抜いてもなかなか痩せられない、停滞期に入ってしまい長引いている…というケースは、体が飢餓状態を察知しているとも考えられます。極端な制限はかえって太りやすい体質へと切り替わるため注意が必要です。
一方で、リバウンドのリスクにも注意しなければなりません。糖質を抜いているあいだはお菓子や主食となる食品を減らさなければならないため、ストレスがかかります。
「あれもこれも食べたい」という気持ちになり、ダイエット中にも関わらず暴飲暴食を行ったり、ハイカロリーのものを口にしたりすると、飢餓に近い状態の体が脂肪を取り込みやすいため、リバウンドを起こす可能性が高くなります。
炭水化物抜きダイエットを行う場合の食材選び
炭水化物抜きダイエットを始めるときは、糖質を含むものに注意しながら慎重に食材を選ばなければなりません。ここからは、ダイエット中に避けたい食材と積極的に摂りたい食材についてチェックしていきましょう。
避けたい食材
ダイエット中は、ご飯・パン・めん類のような炭水化物が多く含まれる食材を避けるようにしましょう。
ただし、まったく食べないとエネルギーが得られず体が太りやすくなりメンタルにも悪影響が出るため、一日の成人のエネルギー量の50%〜65%程度に摂取量を抑えてください。
たとえば活動量が少ない成人女性なら、一日の摂取エネルギーが1,500kcal前後のため、それの50%〜65%とすると750kcal〜975kcalがエネルギー量の目安になります。炭水化物は1gあたり約4kcalのエネルギー量となるため、750kcalなら187.5g、975kcalなら243.75gに満たない量が目安になります。
「満たない量」としているのは、たとえば750kcalを一日の総摂取カロリー量とした場合、187.5gの炭水化物を摂ると炭水化物以外の食材に含まれるカロリーを含めると750kcalを超えてしまうためです。
その他、お菓子・調味料・飲料・アルコール類など食事以外に口にするものにも糖質が含まれている場合があるため注意が必要です。
積極的に摂りたい食材
積極的に摂りたい食材としては、炭水化物と同じようにエネルギー源となるタンパク質のほか、「まごわやさしい」と呼ばれる以下の食材がおすすめです。
【「まごわやさしい」食材】
- ま:豆(豆類)
- ご:ごま(種実類)
- わ:わかめ(海藻類)
- や:野菜(野菜類)
- さ:魚(魚介類)
- し:しいたけ(きのこ類)
- い:いも(イモ類)
和食の基本とされるこれらの食材は、ローカロリーのものを食材に加えることが大切です。イモ類は糖質を多く含んでいるさつまいも・じゃがいもではなく、里芋や長芋を選ぶと良いでしょう。
関連記事:「まごはやさしい」
炭水化物抜きダイエットを成功させるポイント
炭水化物抜きダイエットを成功させるためには、無理に糖質を減らすのではなく正しい知識やデータを参考にする必要があります。以下に紹介する、3つのポイントを押さえておきましょう。
ポイント①最低限の糖質を摂る
糖質はまったく摂らないでいると、体に必要なエネルギーまで奪われた状態となりさまざまな不調の原因になります。
筋肉にとっても、エネルギー源が失われるために本来のパフォーマンス力が出せなくなってしまい、力が出ない・ふらふらする・イライラ感が続くといったトラブルを引き起こす可能性があります。
どれほど厳しいダイエットでも、エネルギーとして使用する最低限の糖質は摂取するようにしましょう。750kcalの総摂取エネルギーなら187.5g以下までの炭水化物が摂取できるので、ご飯なら100g156kcal、茶碗1杯150gで234kcal程度は問題なく摂取できます。
ポイント②長期的に取り組む
ダイエットは短期間で効率的に成功させるほど注目を集められますが、時間にゆとりがある場合はアスリートのような厳しいトレーニングや食事制限を行う必要はありません。
むやみにダイエットを始めても上手くいくとは限らず、しっかりと計画を立てたほうが成功の可能性が高まります。1ヶ月単位で中長期的にダイエット計画を立て、「夏までに5kg痩せる」「1年で10kg落とす」と決めたら、毎月減らしていく体重の目安を算出し、それに向けた細かい計画や生活習慣、運動量なども考えていきましょう。
ポイント③就寝する4時間前に夕食を終わらせる
一日の最後の食事である夕食は、就寝の4時間前には終わらせるようにしましょう。
就寝中は交感神経が鎮まっており、運動もほとんど行わないため、エネルギーの消費量は格段に落ちている状態です。このとき、胃の中にものが残っていると消化器官は活動を続けなければならず、眠っているのに胃腸だけは残業をしなければなりません。
胃腸が活動しているために眠りが浅くなったり、起きてから胃もたれを起こしたりするほか、エネルギーが使われずに体に残るため、肥満や痩せにくい状態にもなってしまいます。
炭水化物抜きダイエットを始める前に押さえておきたい注意点
炭水化物抜きダイエットを行う際には、以下の3つのポイントにも注意しましょう。
注意点①炭水化物を減らしすぎない
炭水化物の量は極端に減らす必要はありません。一日の総摂取カロリーが750kcalであれば187.5g以下までは炭水化物が摂取できるため、うまく食事をコントロールして食材を組み合わせてみてください。
注意点②タンパク質を摂る
さまざまな活動に欠かせない筋肉は、糖質やタンパク質をエネルギー源としています。太るからといって、エネルギー源になる栄養素をすべて抜いてしまうと筋肉の活動まで阻害されるため、タンパク質に置き換えて活動を維持しましょう。特に脂肪燃焼のために筋肉量を増やす場合は、タンパク質の摂取は必須です。
関連記事:良質なたんぱく質って何?おすすめの食材や一日の目安量を解説!
注意点③食物繊維を摂る
食物繊維は体に溜まる老廃物を外に出す働きがあり、野菜などから積極的に摂っていきましょう。水溶性食物繊維・脂溶性食物繊維の2種類があるため、バランス良く摂取することが大切です。
初心者も安心なスポーツジムのSDフィットネス小倉駅前店では、トレーニングサポートを実施しております。運動面はもちろんのこと、栄養面でも一人一人にあったサポートをしているため、初心者の方でも効果的なダイエットが期待できます。気になる方はぜひ一度体験予約にご相談ください。
炭水化物抜きダイエットが向いている方
炭水化物抜きダイエットは、炭水化物が好きで食事が偏りやすく、肥満気味(または肥満症)の方に適しています。食べ物の好き嫌いが少ない方や、自炊が好きな方も苦労が少なく炭水化物を他の食材に置き換えることができるでしょう。
最低限の糖質を摂って痩せやすい体に繋げる
今回は、炭水化物抜きダイエットの特徴や方法、注意点について紹介しました。まったく炭水化物を摂らない方法は断食にも似ており、体の不調や飢餓状態を引き起こすおそれがあるため、体に必要な最低限の量は摂取するようにしましょう。

栄養に関するアドバイスやダイエット中の相談は、プロのトレーナーやスタッフから指導を受けられます。一人でのダイエットが難しい場合は、ジムでのダイエットメニューも検討してみてはいかがでしょうか。
「SDフィットネス」は、初級・中級・上級のレベルにあわせたトレーニング環境を用意しているフィットネスジムです。
プロのアドバイスを参考にダイエットとボディシェイプに挑戦したい方は、ぜひお近くのSDフィットネスへお越しください!
〔2023年6月19日作成、2026年2月12日更新〕
札幌市白石区のジム・フィットネスならSDフィットネス札幌白石店
津市のジム・フィットネスならSDフィットネス津藤方店
小倉のジム・フィットネスならSDフィットネス小倉駅前店
<体質改善/老廃物排出に効果的!女性に大人気!SDフィットネスの「ホットヨガ」>
監修者

山中 隆博
SDフィットネス
パーソナルトレーナー
山中 隆博
SDフィットネス パーソナルトレーナー
<資格>
- 日本ダイエット検定1級
- プロテインマイスター
- フィットネスマネジメント検定2級、1級学科
<略歴>
大学を卒業後、インストラクターとして大手スポーツクラブへ入社し、300名以上のパーソナルトレーニングを経験。その後、専門学校の非常勤講師やキッズミュージカル劇団総監督を経て、当社に入社。現在はSDフィットネスの統括責任者を担当する傍ら、業界セミナー等にも登壇している。