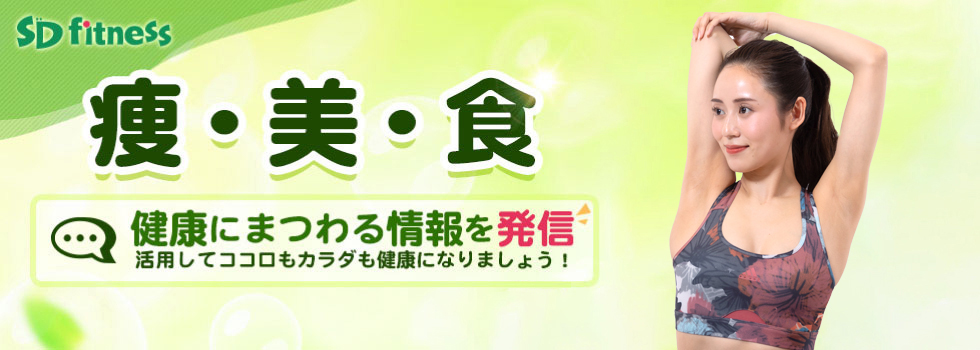健康にいい!七草がゆに含まれる栄養素の種類
カテゴリー:食 - Food -
春の七草、全部言えますか?春の七草には普段よく食べている食材から、この時期特有の食材までいろいろと含まれています。1月7日は七草がゆを食べて、七草の栄養効果に期待しましょう。
目次
■ 春の七草とは
せり なずな ごぎょう はこべら ほとけのざ すずな すずしろ これぞ七草
言えた方の中にも、この植物は何だろう?と疑問を持った方もいるかもしれませんね。
1つずつ見てみましょう。
〇せり(芹)
今もセリの名で親しまれています。宮城県ではセリ鍋、秋田県ではきりたんぽ鍋によく使われます。
〇なずな(薺)
ぺんぺん草の方が親しみがわきますね。かつては貴重な冬の野菜でした。
〇ごぎょう(御形)
母子草。かつては草餅に用いられた草ですが、現在では少なくなりました。
〇はこべら(繁縷)
コハコベと呼ばれます。七草がゆ以外ではあまり食べられていません。
〇ほとけのざ(仏の座)
コオニタビラコと呼ばれます。こちらも七草がゆ以外ではあまり食べられていません。
〇すずな(菘)
カブ(蕪)です。生で食べても、甘酢につけても、鍋に入れても美味しいですね。
〇すずしろ(蘿蔔)
ダイコン(大根)です。冬が旬ですが今では年中食卓にのぼる食材ですね。
すずな、すずしろは、蕪や大根のことだったのかと驚いた人も多いのではないでしょうか。

■ 春の七草の栄養効果
では、これら春の七草にはどのような栄養効果があるのでしょうか。
・解熱効果や咳止め効果が期待でき、寒い冬、風邪をひいた時にも食べたい食材です。
・年末年始の疲れた胃を健康にし、消化促進や食欲増進に有効です。
・利尿作用があるため、老廃物を体外へ排泄することができます。むくみ解消につながります。
・仕事始めの疲労回復に役立ちます。
関連記事:むくみ改善のエクササイズ
■ まとめ
この時期ならではの効果が期待できる春の七草ですね。最近ではスーパーで七草がゆセットとして販売され、手軽に手に入れられるようになりました。
江戸時代に広まった「邪気を払う」習慣ですが、現代においても、年末年始に引き起こしてしまった不調を整えるいい風習です。お粥はもともと消化が良いので、是非、七草がゆを楽しんでみてください。
SDフィットネス津藤方店、青森浜田店、小倉駅前店では、食生活の見直しや、ひとりひとりにあった健康維持の方法について指導を行っております。気になる方は、ぜひ一度体験予約をご相談ください。
【2017年12月17日作成、 2024年12月12日更新】
札幌市白石区のジム・フィットネスならSDフィットネス札幌白石店
津市のジム・フィットネスならSDフィットネス津藤方店
小倉のジム・フィットネスならSDフィットネス小倉駅前店
<身体の疲れを強力にサポートしてくれるクエン酸飲料「BODY RECOVERY」>
<たった2ヶ月で理想のカラダに!完全マンツーマン型のダイエットプログラム「SLIT」>
監修者

山中 隆博
SDフィットネス
パーソナルトレーナー
山中 隆博
SDフィットネス パーソナルトレーナー
<資格>
- 日本ダイエット検定1級
- プロテインマイスター
- フィットネスマネジメント検定2級、1級学科
<略歴>
大学を卒業後、インストラクターとして大手スポーツクラブへ入社し、300名以上のパーソナルトレーニングを経験。その後、専門学校の非常勤講師やキッズミュージカル劇団総監督を経て、当社に入社。現在はSDフィットネスの統括責任者を担当する傍ら、業界セミナー等にも登壇している。